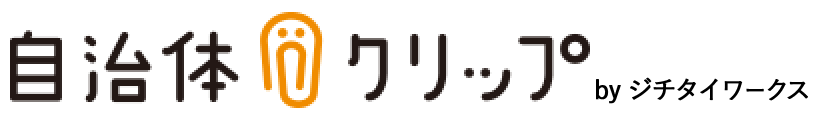ニセ電話詐欺から身を守るための3つのポイント(広報さくら 平成30年1月号)

毎年、全国で大きな被害を出している犯罪といえば「ニセ電話詐欺」。地域によっては「ウソ電話詐欺」なんて言うこともありますし、ちょっと前までは「オレオレ詐欺」なんて呼ばれていました。
いずれにしても一向に数が減らないどころか、ますます被害件数や被害額が拡大しています。
今回ご紹介する佐賀県小城市の「広報さくら」では、ニセ電話詐欺を見抜くポイントや被害に合わないための行動ポイントが掲載されていました。
「自分は大丈夫」という人にこそ、今一度確認してほしい内容です。それではさっそく見てみましょう。
身を守るための3ポイント
佐賀県内ではここ数年、毎年1億円をはるかに越えるウソ電話の被害が出ています。平成29年度の被害額も、11月の時点ですでに1億3,000万円。

これほど被害が減らないのは、ニセ電話が電話一本でお金をだまし取れるため。そして実際に被害にあった人たちが「自分がまさかだまされるとは」と語るほど詐欺の手口が巧妙だからなのです。
ニセ電話詐欺から身を守るために、まずは以下の3つの実践を身に付けることから始めてみましょう。
①留守番電話を利用する
ウソ電話詐欺の犯人は、自分の言葉を録音されることを嫌います。また会話を録音することで、内容を冷静に聞くこともできます。
②非通知着信を拒否する
ほとんどのウソ電話は「非通知」でかかってきます。非通知の着信を拒否することで、そもそもの詐欺のきっかけを防ぐことにつながります。
③お金の話が出たら電話を切る
電話でお金の話が出たら、ほとんどの場合は詐欺です。もし電話の相手がお金の話を切り出したら「かけ直すので番号を教えてください」と告げていったん電話を切り、家族や友人、警察に相談しましょう。

その電話、ニセ電話かも!
ニセ電話詐欺を見分けるキーワードについて、もう少し詳しく見てみましょう。
多くのニセ電話には共通する特徴があります。たとえばこんな言葉が出てきたら、詐欺の可能性大です。
「お金を還付するからATMへ行って」
「コンビニでギフト券を購入して」
「現金をレターパック・宅配便で送って」
「急いでお金を振り込んでほしい」
「通帳、印鑑、キャッシュカードなどを預かります」
こうしたキーワードを聞いたら、まずは誰かに相談することが大切です。また警察・弁護士・行政機関・銀行の名前を出されても安易に信用しない、身に覚えがない話には関わらない、自分の情報を相手に伝えないことも重要です。
また、ニセ電話と思われる電話を受けてしまったら、曖昧な言葉を使わずにはっきり断るようにしましょう。

そして最後にもうひとつ。もし「ニセ電話かも」と思う電話を受けた場合はすぐに家族や周りの人に相談し、実際に詐欺に遭った場合は警察に相談するのを忘れないでください。
詐欺を甘く見ないで
ニセ電話は巧妙・大胆です。知識を身に付けるのはもちろん、「自分なら大丈夫」などと思わず必ず周りの人や警察に相談する心構えを持ちましょう。手口を知っているからといって、簡単に暴けるほどニセ電話の犯人は甘くありません。
加えて、広報紙などに掲載される地元の自治体からのお知らせや、警察からの情報収集も欠かせません。
自分や身の回りの人の身を詐欺から守るには、普段からの心がけが重要!詐欺を甘く見ずに、この機会に自分の行動をしっかり見つめ直してみませんか?
「広報さくら」平成30年1月号
http://machiiro.town/p/29595#page/4
アプリで読むにはこちら
※マチイロが起動し、自動的にダウンロードが開始されます(iOS版のみ)
広報紙をもっと身近に
マチイロは自治体が発行する広報紙をいつでもどこでも読めるアプリです。
地域の魅力的な情報をぜひご覧ください!