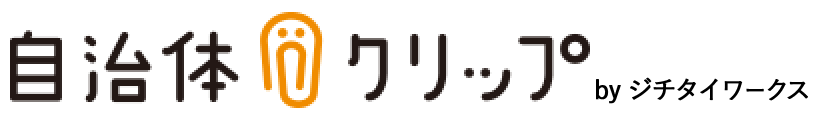【レポート】民間営業と自治体営業の違いとは?

自治体営業を担当する中で、民間との違いに戸惑いを感じている皆さん。この違いを知らないまま営業活動に取り組んでいると、思うように成果が上がらないこともあるかもしれません。そこで今回は「民間営業と自治体営業の違いとは?」と題して、元自治体職員の種子田から、自治体の特徴や自治体営業のポイントについて、分かりやすくお伝えします。
この記事を書いた人

株式会社ジチタイワークス ビジネス開発課 課長 種子田 宗希
約10年間、宮崎県小林市役所にて勤務。農業、観光、企画等、官民連携業務に従事。その後、株式会社ホープ入社。広告営業、自治体営業、新規事業開発等に従事し、現在は株式会社ジチタイワークスにて、官と民のマッチング支援を行っている。
本記事のゴール
自治体・自治体職員の組織風土や考え方を理解し、営業に活かしていく
「自治体とお仕事する」となりますと、自治体(官)の生態系、そこで働く人々の思考法を知っておく必要があると思います。民間企業と違い、官は利益の追求が主目的ではないので、その辺りを含めたお話をさせていただきます。また、我々の契約実績として、約1100の自治体様とお取引があるので、そこで培った知見もお話させていただけるかなと思います。
官民の違いから捉える自治体の特徴
自治体の「官」と我々の民間企業の「民」の違いから、官の特徴を5つ挙げさせていただきます。

1.倒産がない
北海道夕張市のような債務超過のケースはありますが、それでも夕張市という市組織がなくなることはありません。これは良い悪いではないのですが、自浄作用が働きにくいという特徴はあると思います。
2.競合がない
自治体同士には競争がないので、現状維持バイアスがかかりやすい組織体系なのかなと思っております。
3.規制が多い
やはり法律に基づいて仕事をするので、やっていいこと・悪いことが必ずルールで定められています。何より税金を使う以上は、民間企業における稟議という規制よりも、はるかに大きな規制がかかっています。ここで言う規制としては、役所内での稟議や決裁、議会での同意が挙げられます。議会は、基本的に年4回あり、そこで同意をもらわなければ予算は使えません。「3カ月タームでしか稟議がない」とも捉えられるので、スピードは遅くなりがちかなと思います。
4.予算重視
成果よりも予算に矢印が向きがちです。例えば「○○市の来年度予算額は●億円です」「来年度の重点施策はこうです」と、いくらの予算を組んだかは大々的に報道発表されます。でも、組んだ予算がどういう結果を生んだかは基本的に発表されません。もちろん、会計の締めはあるので、議会の中で報告はありますが、予算がどういう効果を生んだのかは公表されません。上場企業であれば、計画を出せば決算発表があり、そこが評価のポイントにもなるわけですが、行政にはそれがありません。なので、成果よりも予算重視になりがちで、自治体職員も成果をまだ重視しきれていない環境になっているかなと思います。
5.税金(先取)≠住民
先に収入が入る構造になっているので、売上と顧客ニーズが紐づきにくいという特徴があります。民間企業であれば、お客様が購入してくださって初めてサービスを提供できるので、「このサービスは良さそうだ」という実感を持っていただくことが先になります。なので、お客様のニーズを非常に大事な観点として商品設計をすると思います。でも、行政の場合は、先に税金をいただくことが確定していて、ある意味「富の再分配」の役割なので、ニーズを満たすために税金を使おうというスタートではないんですね。それが1つの要因となって、ニーズの乖離が生まれることもあるのかなと思います。
営業の時、この5つのポイントを頭の中に入れて話をしていただくと、「だから行政の方はこういうことをおっしゃるんだ」とか「意思決定が遅いのは規制が多くて議会の同意がたくさん必要だからだ」ということも分かりやすくなると思います。
自治体職員の思考の特徴
先ほどの官の特徴を基に、今度は自治体職員の思考の特徴をお話します。

1.社会課題解決 > 利益
官民連携に伴う職員の考え方は、「私もそう思っていた」という前提なんですが、企業とタッグを組む時の判断軸として、利益だけで考えているわけではありません。社会課題の解決がミッションなので、その政策で10人しか恩恵を受ける人がいないとしても、例えば障害者向け政策や母子家庭向け政策だとするなら、分母は少なくてもお金をかけるべきものはあるので、必ずしも金額や多数決の論理だけで解決する状況ではないです。
2.適正発注 > 1円でも安く発注
「適正発注」を重視するという考え方があります。安ければいいというわけではないんです。役所が民間企業に仕事を発注する目的として、政策実現もありますが、それと同時に経済をまわすという論点もあります。なので、安い価格で業者さんが泣いてしまうことがあると経済をまわす目的が達成できないので、適正価格で発注しようとします。
3.前例主義や法令順守 > 新規性
「前例主義や法令順守」思考です。これは、私は悪いことではないと思っています。法律は当然守らないといけないですし、税金を使う以上、失敗はできないので、どこかの自治体で成功した事例や前年度に取り組んだ同じ事例を手掛ける方が、安全に期待される効果を狙えるので、そういった意味では前例主義・法令順守にならざるを得ないという特徴があります。
自治体ビジネスのメリット
次に、民に焦点を当ててみましょう。民間企業側から見た自治体ビジネスのメリットを説明します。

1.信用・ブランド力のUP
これは役所の目立つ特徴の1つかなと思います。そもそも役所は、私の言葉で言うと「嘘をつかない」「社会的に曲がったことはしない」という信頼感はあると思います。「役所が非効率だ」「もうちょっと良くなったらいいな」という想いを抱くことがあるかもしれないんですが、役所が何か反社会的なことをすることは考えられないと思います。そういう役所と仕事をしていることは、その会社も「公共的な分野に携わっている」「社会的意義のある政策に関わっている」といった信用を得ることができます。実際に自治体も業者さんを選ぶ時は、業者登録や滞納調査、暴力団審査をするので、それも含めて信用を印象づけることができます。

実際によくBtoBの企業である事例としては、もともとBtoBに商材を展開していたけど、BtoGの実績ができたことによって「当社は自治体とも仕事をしている会社なんです」というセールストークが可能になり、認知度や信頼を獲得しやすくなる効果が見込めます。
2.公平・公正
業者登録や一定の条件を満たせば誰でも参入できるところが、公平なところだと思います。特に国の場合が特徴的なんですが、大企業だけに発注が偏らないように、行政はかなり気を遣ってコントロールしています。国の官公庁であれば、企業の発注の中にランクを設けています。簡単に言えば、Aランクであれば、資本金が数十億円以上じゃないと入れないといった仕組みなんですが、Aランクの企業ばかりが落札・受注しているわけではなくて、入札は資本金がまだ少ないC~Dランクの企業しか入れないようになっています。なので、国の統計的にも、大企業と中小企業の発注割合は、おおよその金額で半々、年によっては中小企業の発注の方が多くて、中小企業でも参加できる状況になっています。
3.安心安全
自治体の社会的意義から、未払いなどの対応・法的違反のリスクがありません。また、倒産の心配がないため、貸し倒れのリスクもありません。
自治体の特徴を押さえた「自治体営業の基本」
自治体営業の基本は3つです。
まず大前提として、自治体と仕事をする方法は、営業するか入札に参加するかの2つしか基本的にありません。
①前年度から営業活動・予算取りと②公示された案件を応札です。

営業活動と入札参加、双方のメリット・デメリットをまとめると、このような形になります。
営業活動は営業にコストがかかる一方、入札参加は、入札がすでに上がっているので、ホームページさえチェックしておけばスピード感はあります。ただ、発注条件・金額が全て固まった状態で上がるので、上がった入札案件が自社にマッチしていない場合があるのがデメリットになります。
そこで今回は、①前年度から営業活動・予算取りに絞ってお話します。
ポイント1 自治体市場の開拓は予算申請から逆算した営業を行う
営業活動を行う際に、自治体市場のポイントとして、予算を取る時期が決まっていることが挙げられます。

秋から冬にかけて予算申請時期があるんですが、この時期に予算を取ってもらわなければ、翌年度の予算、4月以降の仕事にはならないとご理解いただければと思います。なので、「前年度から営業活動・予算取り」する必要があります。
ただし、補足として、当然自治体側も、9~12月の予算申請時期だけで、来年度の見通しをすべて立てられるわけではありません。年度途中で「この政策もしなくてはいけない」「こっちにもお金を配分しないといけない」ということがあります。そのために6月・9月・12月・3月に補正予算を設けています。世の中に公表されいてる資料では9月・12月しか取り上げていないんですが、これには理由があります。確かに6月補正はあるんですが、基本的に役所の方は6月補正を嫌がってしないです。なぜかと言うと、年度が始まってすぐにいきなり予算を変更することは、議員から指摘されることが多いからです。「見通しが甘かったんじゃないか」「なんで年度が始まってすぐに軌道修正するんだ」となりがちなので、私も職員時代は「6月補正はなるべくしないで、9月・12月でもいいのであれば、その時にあげてくれ」と上司から指示されていました。また、3月の補正は年度終了間際なので、予算を取ったとしても使えません。3月議会は目的が違って、補正をするための議会ではなく、来年度の予算を認めるための場なので、実質的には9月か12月というのが補正予算の性質です。
まとめると、基本的には予算申請時期から逆算して営業スケジュールを立てましょう。

実は、2~3月は来年度の予算が内部で固まっている時期なんですね。なので、この時期にプロモーションをかけると、いち早く先行して自治体に認知してもらえます。職員だった時を振り返ると、2~3月は「予算はすでに通過した」「この事業は4月以降に実施できるんだな」と理解していました。
そして、議会は重要な場なんですが、予算が否決されることはほとんどないんですね。仮に否決されてしまうと、社会政策や社会保障的もすべて止まることになってしまい、住民生活に多大な影響があるので、基本的に否決されることはありません。なので、4月以降でないと実務上は何もできませんが、内部では2~3月に「この事業・政策は実現できる」という意識になっているので、そのタイミングでしっかりコミュニケーションをとれれば、職員さんから「資料をもらえませんか」「見積もりをもらえませんか」という話になるので、そういった意味で2~3月のプロモーションもオススメしています。
ポイント2 予算編成方針を押さえて、自治体に刺さる提案をする
自治体営業と民間営業の最大の違いとして、自治体の情報は基本的に公開されていることが大きな特徴かなと思います。税金を使う以上、当該自治体が何を目指していて、何に困っているかが公開されています。その1つが「予算編成方針」です。
予算編成方針は、毎年秋ごろに、どの自治体も出します。財政部局が予算をつくる上での全課への指示書にもなります。「こういうところに気をつけながら予算を組んでください」という方針ですね。つまり、予算を獲得するためには、その自治体の予算編成方針を理解し、それに基づいて提案すると、かなり刺さりやすくなります。
例えばどういうことが書かれているか、中身を見ていきます。

■自治体の財政状況
普通交付税 H25 : 89億円 → R2 : 79億円
■大方針(歳出)
・「第2次小林市総合計画」の実現を目指すことを基調
・ ウィズコロナ、ポストコロナ、デジタル化を見据える
・「既存事業を全て同一規模で継続」しながら「変化対応」は不可能
・ 各部局一般財源 前年比92%以内
・「健康都市プロジェクト」及び「人口減少対策プロジェクト」に戦略的に取り組む
・新規事業について
目的、成果、費用対効果及び後年度負担などを検討することはもちろん、
必ず既存事業との比較検討を行い、既存事業より優先度が高いと判断した場合は、
既存事業の見直し等によって生み出した財源により、要求する事。
・公共ファシリティマネジメントの推進
公共施設の適正管理を推進、市有財産の有効活用を図る
これは私の地元、宮崎県小林市の予算編成方針から抜き出した内容なんですが、まず、交付税が減っていて、自治体の財政状況がひっ迫していることが分かります。そして、それを踏まえて、「こういうことを重視して予算を組みなさい」「こういうことを重視しない場合、予算は認められませんよ」ということを財政部局が言っています。なので、各課は、この方針を重視して予算を組みます。この方針に合致している予算であれば議会で通過しやすいと理解していただいて問題ありません。
例えば、「『第2次小林市総合計画』の実現を目指しましょう」「ウィズコロナ・ポストコロナで、デジタル化を積極的に取り入れていきましょう」。それで、色んな細かい内容も書かれています。「『既存事業を全て同一規模で継続』しながら『変化対応』は不可能」、要は追加予算を組まないでほしいという話ですね。予算は前年比92%以内、「8%削りなさい」と言われています。そして「市長が目指す重点プロジェクトは戦略的に取り組みなさい」というような感じですね。
ちなみに補足ですが、これは小林市だけでないという認識で問題ありません。どの自治体も基本的に同じ方針で、この方針が自治体にとって最大の懸念ポイントなので、ここを補足するような営業トークやセールスをされると自治体は非常に理解しやすいです。例えば、目的・成果・費用対効果及び後年度負担はしっかり検討してほしいと伝えています。始めたからには事業を簡単に止められないのが行政です。一度始めた政策を1年で止めてしまうと「あれは何だったんだ」と議会から指摘される一方、後年度もずっと予算がかかってしまうものは自治体にとってやりにくいわけですね。なので、それが意味のある事業なのか、既存事業と比較してどうなのか、優先度は高いのかは、シビアに見られます。
仮に、観光課にSNS広告による観光プロモーションを営業するとします。そうなった時に、自治体は広告費だけを見て比較しているわけではありません。先ほどお話した通り、前年度92%以内の予算に収めないといけないので、他広告との比較もしています。また、観光予算には、観光施設の維持管理費や観光協会などに案内スタッフを置く人件費など、色んな予算があります。人件費や広告費を予算と見比べて「果たしてSNS広告はやる意味があるのか」と、事業全体の相対的評価で最終的に優先順位を決断していくので、単純に「広告の効果があります」だけよりも、「他に取り組んでいる施策と比較した中でも、この事業は一番やる意味があります」みたいなロジックがあった方が、最終的に前年比92%以内に予算を収めないといけない自治体としては判断しやすくなり、財政的に説明しやすくなります。
ポイント3 自社サービスにあった受注方法を選ぶ
自治体の受注方法は入札や随意契約など、色んな種類があります。
今回は営業に活動に絞ってお話いていくので、3つの受注方法について説明します。

①随意契約
随意契約を一言で表すと、事務を簡素化した契約方式です。入札は正直ものすごく事務工数がかかるんですね。「何日以内に業者に通知しなさい」「こういった書類に基づいて価格を決めなさい」など、全てのルールが法律でしっかりと決まっています。そうなると何枚も書類をつくらないといけないので、私の体感ですが、随意契約と比べると約10倍の工数がかかります。役所の事務工数も無限大ではないので、効率的に業務を回そうとすると、少ない企業だけを見積もり比較して随意契約することもあります。
こういったやり取りの中で「決裁権限はいくらまでなんですか」と聞かれることがありますが、自治体はきちんと法律で規定されています。【引用:地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)】

地方自治法施行令によると、都道府県及び政令指定都市と市町村では金額は違いますが、工事だったら130万円以下であれば、課長・部長決裁で可能だったり、二者随契が可能だったりと決まっています。
自社サービスの特性が地方自治法施行令に当てはまるものであれば、自治体の意思決定のハードルが低く、決裁が通りやすいということもあるので把握しておくと良いでしょう。
②包括連携協定
入札等をせず、自治体と企業が課題解決に向けて連携を行う方法です。簡単に説明すると、お互い協力的に政策を進めましょうといった取り組みです。
【取り組み事例】
福岡県小郡市と官民連携協定を締結
① 官民連携に伴う情報収集効率化支援
② 官民連携セミナーの開催
③ 小郡市の官民連携情報の発信

予算の敷居が低く、入札や随意契約などの細かい手順が不要なので、取り組みやすい受注方法です。ただ、実績が伴わない場合もあるので、注意してください。
③実証実験
実証実験は、その名の通り、実験的に政策を実施するための方法です。
自治体側は予算を一切負担しなしで、企業がサービスを展開するフィールドを提供したり、広報や職員派遣等で協力したりします。行政としては税金がかからないので、議会を通さなくていいメリットがありますし、企業からすると、行政と仕事をした実績ができたり、行政をフィールドとした検証もできたりするので、企業と行政、お互いWin-Winの取り組みとなっています。
また、自治体が事業を募集し、専門窓口があるケースもあります。例えば福岡市には、官民連携の実証実験を推奨する専門部署があります。
 福岡市 mirai@(ミライアット)トップページ
福岡市 mirai@(ミライアット)トップページ「年間数十件の実証実験をやります」と目標を掲げている自治体も非常に多いので、そういった部署にアプローチしていくといいかなと思います。
ちなみに、私の地元である宮崎市では2022年1月に40歳の市長が就任しました。その方は「実証実験は積極的に進めていく」と当選直後の方針説明でおっしゃっていました。革新的な市長は官民連携のタッグを必須だと思っていますし、そういう実証実験が一般的であることは浸透しているので、若くて革新的な首長であれば、営業先候補として優先的に選ぶといいのではないのかなと思います。
まとめ
官民の違いから捉える自治体の特徴
・倒産がないため、自浄作用が働きにく、自己組織に向きやすい
・現状維持を好み、非効率
・規制が多いため、スピードが遅い
・予算重視(予算>成果)
・売上と古曲が紐づきにくく、ニーズ乖離が生まれやすい
自治体職員の思考の特徴
・利益より「社会課題解決」重視
・低価格より「適正発注」
・公金で行う以上保守的なため、前例主義で法令順守する
自治体ビジネスのメリット
・信用・ブランド力UP
・公平・公正
・安心安全
自治体の特徴を押さえた「自治体営業の基本」
ポイント1:自治体市場の開拓は予算申請から逆算した営業を行う
ポイント2:予算編成方針を押さえて、刺さる提案をする
ポイント3:自社サービスにあった受注方法を選ぶ
※こちらの記事は2022年2月に実施したセミナーの書き起こし記事です。
セミナー動画オンデマンド配信中!
本記事の元になったセミナー「民間営業と自治体営業の違いとは?」をYouTubeにて配信中です。下記よりご覧いただけます。
最後に
ここまで、自治体職員の思考やスケジュールの違いなどを取り上げ、民間営業と自治体営業の違いについてお話してきましたが、これらの情報を事前に理解しておくことで、より的を射た形で自治体営業を実行することができるようになります。
ただ、それらの違いを把握した上で、自治体市場の特色に合ったアプローチをする必要があるとなると、「正直大変だな」と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで当社では、今まで培ってきた自治体ノウハウ・ネットワークを活かし、自治体営業支援サービスを展開しております。
※メディアレーダー会員の方は、こちらから媒体資料をDLいただけます。
自社に合う自治体へのアプローチ方法が分からない、自治体営業が思うようにいかないなど、自治体営業に関するお悩みがありましたら、いつでもご連絡ください。
お問い合わせ
株式会社ジチタイワークス ソリューション営業課
マーケティング担当:中山・林・諸藤
Tel:092-716-1480
Email:btog@zaigenkakuho.com