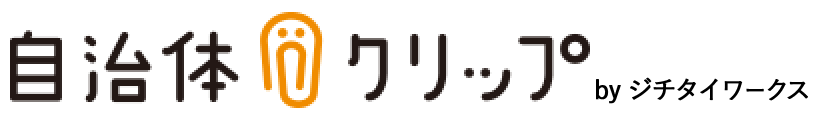地方消費税とは?地元貢献のために知っておきたい知識

商品やサービスを購入したら支払うことになる消費税は、消費者にとってたいへん身近な税金です。そんな消費税に、地方消費税というものがあるのをご存知でしょうか。
地方消費税は、地方自治体の貴重な財源の1つになっています。けれども、「地方消費税っていつ払ってるの?」と疑問に思う人も多いことでしょう。
ここでは、地方消費税の仕組みや地元に貢献する方法について、分かりやすくまとめます。
知らないうちに払っていた?地方消費税とは?
消費者がお店などで商品やサービスを買うと、必ず消費税がかかりますよね。消費者が支払った消費税は、商品やサービスを売り上げた事業者の収入にはなりません。事業者は消費税を一時的に預かっているだけで、後日税務署に納付する義務を負っています。税務署を経由して、日本中の消費税がいったん国に集まり、その一部が各都道府県に分配される仕組みです。
各都道府県に分配された消費税のさらに半分は、各市町村に分けられます。このように消費税は、地方自治体の財政を支える重要な収入源になっているのです。けれども、ふつう消費者が消費税を払うとき、いちいち地方消費税を意識したりはしませんよね。実は消費税は、国税部分と地方税部分(地方消費税)という2つの部分から構成されているのです。
つまり、消費者は、知らず知らずのうちに地方消費税を支払っている、ということになります。
地方消費税はどのくらいの割合で消費税に含まれているの?
消費税のうち、地方消費税はどのくらいの割合を占めているのでしょうか。2014年4月1日から、消費税は8%になりました。このうち1.7%が地方消費税部分であり、残りの6.3%が国税部分です。2015年に実際に徴収された消費税収は17兆4263億円なので、計算上その「8分の1.7」にあたる3.7兆円ほどが地方消費税部分ということになります。
消費税が3%から5%に上がった1997年時点では、4%が国税部分で、1%が地方消費税部分という割合になっていました。また、2019年10月1日以降に、消費税は10%に引き上げられることが決まっています。その場合の内訳は、地方消費税は2.2%、国税部分は7.8%になる予定です。地方消費税は、すべて社会保障に使われることになっており、一般財源とすることはできません。
けれども、地方税収の20%ほどを占める地方消費税は、地方自治体にとってなくてはならない収入の1つです。
高齢化社会を迎え、社会保障のための財源確保に苦しむ地方自治体も少なくないため、地方消費税をどのように各都道府県に分配するかについて盛んに議論が行われています。
地元に貢献するなら地元でショッピング
消費者が県境をまたいで買い物をすると、地方消費税がどう扱われるのか気になりますよね。消費税を払ったのは県民でも、事業者が県外であれば県外の税務署に納税されてしまいます。これは公平とはいえないでしょう。これまで、地方消費税の分配では、各都道府県の「従業員数」「消費額」「人口」という3つの基準(清算基準)をもちいて分配金額を決めていました。
ところが、これらの数が多い大都市ほど有利なことは明らかで、批判も少なくありませんでした。この問題を解決するため、2018年の税制大綱により、大都市に有利になる基準の比率を引き下げることが決まっています。
また、「従業員数」基準は廃止され、「人口」と「消費額」を50%ずつ勘案して分配することになったのです。
この影響で、東京の税収は1千億円ほど減り、不満の声も出ています。
そもそも、消費実態を正確にデータに反映させることは難しいため、確実に地元に貢献したいなら地元で買い物をするのが一番です。地元の「消費額」を増やせれば、分配される地方消費税の額は増え、地元自治体の財政状況は良くなります。ひいては、地元自治体が実施する社会保障業務が充実し、よりよいサービスが受けられるようになるでしょう。
逆に地元自治体の財政が傾けば、受けられるサービスも受けられなくなってしまいます。地元に地方消費税が多く分配されるよう、ショッピングはできるだけ地元でしたいものですね。